







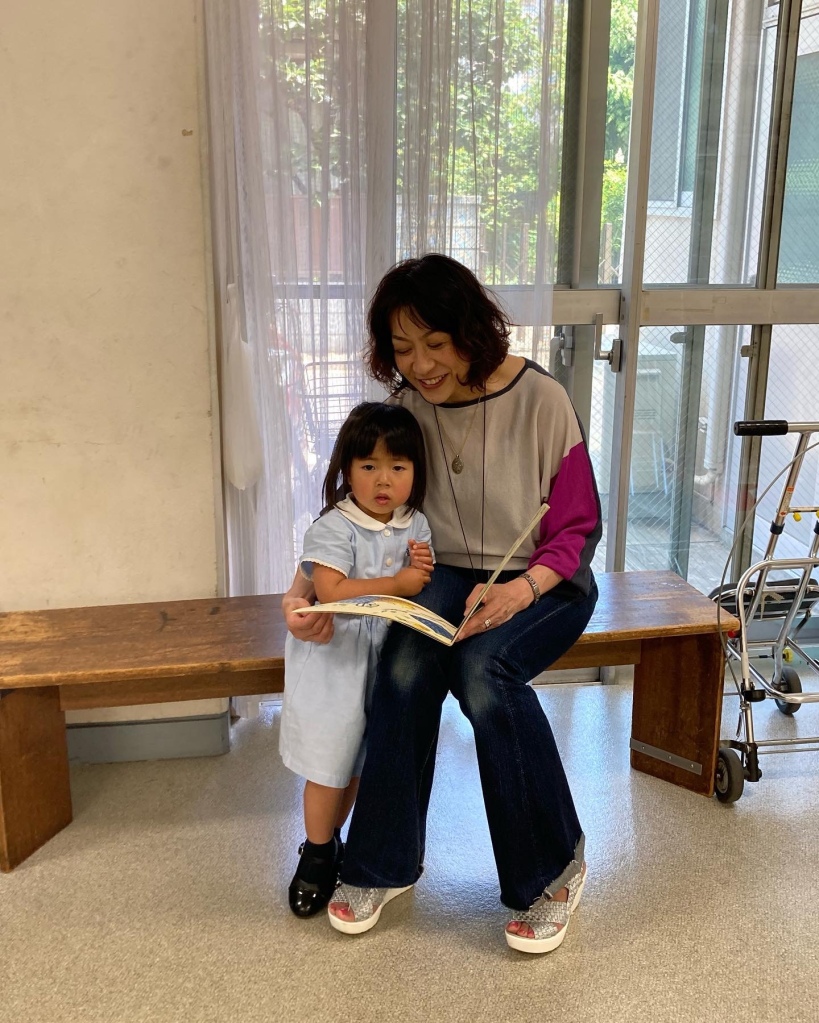




6月4日(日)三位一体主日・聖霊降臨後第1主日
創世記 1:1-2:3; IIコリント 13:11-13; マタイ 28:16-20
先週の日曜日、聖霊降臨日をもって、2月22日の灰の水曜日から始まった長いイースター・シーズンが終わりました。
しかし、今日はまだOrdinaryと呼ばれる「普段」の季節、祭色で言えば緑の季節の日曜日ではありません。聖霊降臨後の第1主日は三位一体主日という祝日です。
三位一体というのはキリスト教の教義の一つですが、これは同時に、キリスト教のあらゆる教義の頂点として位置付けられてきました。
人は昔から神について何らかのことを知ってはいたけれども、三位一体という教義こそが、神についての最も完全な理解を示している。そう教会は主張してきました。
今日は、三位一体主日の第一朗読に、なぜ創世記の1章から2章冒頭までの、こんなに長い箇所が読まれるのか、その種明かしをしたいと思います。
今朝の福音書朗読で読まれたマタイ28章の20節で、イエス様は「世の終わり」まで弟子たちと共にいると約束しておられますが、第一朗読の創世記の箇所は「世の始まり」、天地創造の物語です。
この朗読箇所の選択から、聖餐式聖書日課を編纂する人たちは、「三位一体の神は、天地創造の初めから、世の終わりまで、いつも働いておられる」と言いたかったのだろうということがわかります。
しかし、三位一体という教義の「根拠」として創世記 1章1節から2章3節が選ばれる理由は、その中のたった1節、1章26節にあります。
「26 神は言われた。「我々のかたちに、我々の姿に人を造ろう。そして、海の魚、空の鳥、家畜、地のあらゆるもの、地を這うあらゆるものを治めさせよう。」」この1節です。
なぜこの1節が、三位一体の教義の正しさを保障するテキストであるかのように扱われるのか。それは、2世紀後半以降、教義の発展に大きな影響力を持っていた教父と呼ばれる人たちの多くが「我々」と言う表現の中に、三位一体の神が現れていると「解釈」してきたためです。
それがどんな人たちかと言いますと、アレクサンドリアのクレメンス、マリウス・ヴィクトリヌス、プルデンティウス、クリュソストムス、誰もが知っているアウグスティヌス、ルスペのフルゲンティウス、リスボンのポタミウスといった人たちです。
第一朗読で読まれた箇所の中には、「神」という言葉が35回も出てきますが、神と訳されているのはヘブライ語の ‘אֱלֹהִים’ という言葉です。実は、この ‘אֱלֹהִים’ というのは複数形の名詞です。ですから、名詞の形だけから判断すれば、本来は「神々」と訳すべき言葉です。
それにも関わらず、 ‘אֱלֹהִים’ という言葉を、大抵の場合、「神々」と訳さずに、「神」と単数形にして訳すのは、動詞に単数形が用いられているからです。
名詞は「神々」を意味する複数形なのに、動詞に単数形が使われるようになったのは、ものすごく単純化して言えば、イスラエルの人たちの神理解が、多神教から一神教へと変化したためです。
歴史的に言えば、イスラエルの「先祖」たちも、周辺諸国の人たちと、多神教的世界観を共有していました。
モーセによってエジプト地からイスラエルの民を導き出した「ヤーヴェ」という神は、多くの神々の中の、一つの神として認識されていました。
多くの神々がいるけれども、イスラエルの民は、この「ヤーヴェ」という神に選ばれ、エジブトの地から導き出された。だからイスラエルの民は、他の神々にうつつを抜かさず、「ヤーヴェ」にのみ忠誠を尽くさなくてはならない。そう考えられていました。
しかしイスラエルの人々は、他の民族や国々の中で「神々」と呼ばれているのは、本当は神ではなくて、イスラエルの神こそ、唯一の、世界をつくられた神だと理解するようになりました。
ところが、イスラエルの人たちが「神は唯一だ」と認識するようになった後も、 ‘אֱלֹהִים’ という言葉を使うのは止めよう、ということにはなりませんでした。
ちなみに、ヘブライ語にも単数形の「神」という言葉があります。それは ‘אֵל’ という言葉です。
この「神」を表す単数形の ‘אֵל’ という言葉は、旧約聖書全体の245節に出てきますが、複数形の ‘אֱלֹהִים’ の方はその10倍以上、2606節に出てきます。つまり、使い慣れてきた言葉を、そんな簡単に捨てることはできなかったわけです。
しかしイスラエルの人たちは、 ‘אֱלֹהִים’ という複数形の名詞を、唯一の神を表すために使うための方法を考え出しました。それが、動詞を単数形にすることでした。
名詞は複数形でも、動詞を単数形にすることで、今まで使い慣れてきた ‘אֱלֹהִים’ という言葉で、唯一の神を表すようにしたのです。
ところが、創世記1章26節では、おかしなことが起きています。「神は言われた」。この「言われた」という動詞は、原則通り、3人称単数の男性形になっています。
しかし次の、「我々のかたちに、我々の姿に人を造ろう」の「我々は造ろう」は、1人称の複数形なのです。
今現在、私たちの手元にあるテキストの文脈からは、「我々のかたちに、我々の姿に人を造ろう」と言っているのは、直前に出てきた ‘אֱלֹהִים’ だとしか読めません。
そうすると、当然のことながら、なぜ「私のかたちに、私の姿に人を造ろう」ではなくて、多神教的に理解されることになる「我々のかたちに、我々の姿に人を造ろう」となっているのか、という疑問が湧いてきます。
残念ながら、この疑問に対する明確な答えはありません。しかし確実に言えることは、「創世記1章26節にキリストや聖霊が現れているという教父たちの「解釈」は、釈義的には100%間違っているということです。
ソシュール以降の構造主義言語学の最大の発見は、言語の意味作用は共時的差異の体系によって支えられているということです。それは、ある時代のある言語体系が何を意味し得るかは、限界づけられているということでもあります。
例えば、「妹」という言葉は源氏物語の時代(紀元後1001-5年)には、男が、同じ母親から生まれた姉妹を指すために用いられました。つまり「妹」はその男きょうだいの姉でも妹でも、どちらでもありえたということです。
しかし、2023年の東京で、私が「うちの次男SにはRという妹がいます」と言ったら、Rは絶対にSよりも年下です。「SにはRという妹がいます」という文を読んで、「RはSよりも年上かもしれない。源氏物語の時代には、妹は姉でも妹でもあり得たんだから。」と言うとすれば、それはアナクロニズム、時代錯誤という過ちを犯しているということになります。
2003年現在の東京で使われている日本語の言語体系の中では、「妹」という言葉は、「男きょうだいにとっての年下の女きょうだい」しか意味し得ません。
ですから、バビロン捕囚以降、紀元前6世紀や5世紀の旧約聖書ヘブライ語が、イエス・キリストや聖霊について語ることはできません。
今日、三位一体主日の説教のポイントは、イスラエルの時代から、教父たちの時代を経て、今に至るまで、神と神の業に関する理解は、絶え間なく変化し続けているということです。
「三位一体」という教義が生まれたのは、教会がヘレニズム世界へと広かってゆき、ヘレニズム的教養をもって、神と神の救いの働きを理解しようとしたからです。
神と神の救いの業についての理解を、常に更新しようとしなければ、教会は今、この時、この世界に生きる人たちとの接点を失い、博物館のような存在になってしまいます。
私たちがこの時代に、この世界で、イエス・キリストによって成し遂げられ、聖霊を通して今も続く神の救いの業に、人々を巻き込んでいこうとするならば、三位一体論を更新しつづけなくてはなりません。
神と神の救いの業についての理解をup-dateし続けることは、教会にとって避けることのできない使命なのです。
そして、神と神の救いの業の理解を無限に更新し続ける試みが、神学と呼ばれる営みです。
聖マーガレット教会が、この時代に、この地で、多くの人々を神の救いの働きの中に巻き込んでいくために、皆さん、どうか神学するクリスチャンとなってください。信仰を「理解」しようとするキリストの弟子となってください。
